バカだけどチンチンしゃぶるのだけはじょうずなちーちゃん

2017年11月24日
オトナ文庫
著:蝦沼ミナミ
画:はましま薫夫
原作:ORCSOFT
そんなこと言っても、なにが解決するわけじゃない。
わけじゃないが、それでも口から漏れ出てしまう。
「あぢぃ……」
益体もない愚痴を漏らしながら、ずるずると重い足を引きずる。
学校指定のワイシャツの下には、男子平均プラス二十キロ分の分厚い脂肪のコート。梅雨明け間もない七月の街は、さながら一ヶ月後の盛夏を先取りしたかのような暑さで全身を茹であげてくる。大量の汗でシャツがべったりと貼り付き、一歩ごとにぬちゃぬちゃと湿った音が鳴る。
「あ、あぢいぃ……」
益体もない愚痴をもう一度。
本当なら、こんな日はクーラーの効いた室内でアイスクリームでもぱくついているべきだ。それこそがピザデブにとっての、正しい夏の過ごし方というものだ。だがそれでも、今日、明日分の食料品ぐらいは確保しておかないといけない。一人暮らしは気楽で快適だけど、こういうときは親のありがたさが──。
「……ま、無駄口叩いても、どうしようもないか」
三度目の愚痴を喉もとで押し止めて、茹だりきった身体をずるずると引きずる。片手にはずっしりと重いレジ袋。食料品の買い出しを終えたそれを自宅マンションまで運んだら、もう外出なんかしない。この土日は、室内に引きこもって自堕落で快適な生活を満喫するのだ──と。
「うっわ……」
そんなことを思いながら歩いていると、コンビニの駐車場にフェラチオが座り込んでいるのが目に入った。
いや、正確に言えば座り込んでいるのは、もはやフェラチオと呼ぶ以外ない、エロエロしいまでにエロい仕草でアイスキャンディーを舐めしゃぶっているエロ女だ。

脱色したロングヘアに、こんがり焼けた褐色肌。ボンキュッボンなワガママボディで、全身是セックスとでも言うべき、ただならないエロさを周囲に振りまいている。そんな肉感的にもほどがある身体を、ショート丈のヘソ出しキャミと膝上二十センチ超のミニスカートに押し込んで座り込んでいるものだから、ギャル服の下からはパンツが、上から立派すぎる谷間が覗いてしまっていた。
厚みのあるぽってりした唇でアイスキャンディーをちゅぱちゅぱと舐め回しているその姿は、さながら「アタシは棒状のモノをしゃぶるのがちょー得意です!」と主張するエロギャルのごとし。とろけたアイスが唇からこぼれ、顎から胸もとへと伝い、肌を濡らす汗に溶けながら乳房の丸みに沿って奥のほうへと流れ込んでゆく──その様子に目を奪われ、思わずコクリと唾を飲み込む。
「はふっ、はむ、んん、ん……」
そんな熱視線にも気付かず、べろんべろんとアイスキャンディーを舐め回す彼女。
物憂げそうな半開きの瞳。汗を吸って乳房に貼りつくキャミソール。だらしなく開いた両膝。小麦色の肌とコントラストを成すパンツの純白色。ああ、もうたまらない。今すぐ家に帰ってシコりたい……でも、もっとこの光景を見ていたい……でも見れば見るほど、今すぐシコりたくなってしまう! 夏の太陽に炙られた頭の中がドロドロにとろけてゆく一方、下半身に熱い血が集まり、ズボンの中がガチガチにこわばってゆく。
と、そのとき、彼女がご開帳状態だった両膝を閉じた。
ガッカリ感とともに顔を上げると、くりくりした瞳がこちらを見返しているのに気がついた。それから目を逸らしつつ、まださらけ出されている胸の谷間に視線を向ける──。
「いやいやいや、もっかい見直すとかありえないし!」
と、そんな不躾な視線を遮るように、目の前のセックスが両手を胸もとにやった。
いや正確に言えば、もはや全身是セックスというほかない、エロすぎる身体の女の子がだ。彼女は棒だけになったアイスキャンディーをゴミ箱に放り込むと、こちらに近づいてきた。ぴょこぴょこと軽快な足取り。しっとりと汗ばんだ太もも。たぷたぷと揺れるおっぱい。さらにもう二十センチばかり視線を上げたところで、エロすぎる身体の上に、よく見慣れた顔が載っているのに気がついた。
「もー。ちょっとは遠慮しなよね。まじまじガン見しちゃって」
「……せっかく見せてくれてるんだから、ありがたく見せてもらおうと思って」
「見せてるわけじゃないし! こーちんって、いい性格してるよねぇ」
大げさにあきれて見せるけど、表情も、声音にも怒気はない。
近づいてきたのは椎名ちえりだった。
豊満にもほどがある肢体で、いつも男子生徒たちの目を大いに愉しませたり、悩ませたりしているクラスメイト。なんでもブラジル方面の血が入っているらしく、亜麻色の髪やカフェオレ色の肌は生まれながらの天然物。ダイナマイトにもほどがあるプロポーションも、そちらの遺伝子のたまものだとか。オスの性本能を直接ぶん殴ってくるような刺激的すぎるボディと、いかにもゆるそうな人柄に惹かれてしまった男どもは数知れず。彼女と直接話したことはほとんどないけれど、経験豊富だの、エンコーでマンションを買っただの、我が校の男子生徒の大半は彼女の手ほどきで童貞喪失しているだの、どこまで本当なのかわからない噂話を幾つも耳にしている。いや、たぶん九割方ウソなんだろうけれど、そんな荒唐無稽な噂も「ひょっとして!?」と思わせてしまうかのような、彼女が暴力的なまでのエロさを備えたオンナであることは、まぎれもない事実なのだ。
「誰かと思った。私服の椎名さん見るの初めてだったから」
「服なんか見てなかったくせに」
せめてもの言い訳を、一言のもとに切り捨てる彼女。
だがやはり気分を害したふうはなく、むしろ楽しげにこちらを見返してくる。
素直で愛嬌のある人懐こい表情──だが、いかにも牝々しい身体つきでそんな顔をされると、あれこれ余計な妄想が膨らんでしまって、下腹のあたりがどうにも落ち着かない。
「会えてよかったよぉ。うちに行ったけど留守だったんだもん」
「うちって……俺んち?」
「うん。それで、ひょっとしたら会えるかもって思って、近くで待ってたんだ」
ずくん、と心臓が弾んだ。
クラスのエロい女子が俺に会うために家まで押しかけてきた? そんなの、童貞の夢物語だ。あるはずのない馬鹿話だ──。
「……なんで?」
「そりゃもちろん、用事があったからだよー。スマホのアドレス知らなかったから、直接来ちゃった」
その馬鹿みたいな夢物語が今、目の前でにこにこ顔を浮かべている。直射日光に脳天を炙られ、牝フェロモンに下腹を刺激され、胸中には甘酸っぱい期待が渦巻き──。
「続きは、こーちんちでね。じゃあ、しゅっぱつしんこー!」
わけもわからず呆けていると、彼女はぐいぐいと背中を押し始めた。
うわっ、手のひら柔らかいっ──!?
彼女の人懐こさと図々しさに面食らいながらも、その心地よい感触だけで、なにもかも許せる気分になってしまうのだった。
室戸浩太は、近所の学園に通う男子生徒だ。
今は親もとを離れ、通学用にワンルームのマンションを借りて一人暮らし。学生の一人暮らしなんてたちまち悪友どものたまり場になってしまいそうなものだが、そうなっていないのは、浩太自身が、あまり積極的に交友範囲を広げるタイプではないからだ。
かと言って、教室でいじめられているというわけでもない。
男子平均プラス二十キロのぽっちゃり体型だが、いわゆる「動けるデブ」というやつで、運動はむしろ得意なほうといっていい。その上、学業のほうは入学以来、常に学年トップクラスに居座り続けている。周囲からはそれなりに一目置かれているし、人づきあいが狭いのはべつに嫌われているわけではなく、一人でゲームやアニメを楽しむのが性に合っているインドア志向ゆえの選択の結果なのだ──と浩太自身は思っている。
だから一人暮らしのマンションも、今まで入ったことがあるのは浩太自身と、父親との二人きり。だが今日、その室内に思いがけない三人目が足を踏み入れた。エロい身体で、エロい格好で、エロい仕草が板についている、まるでエロのかたまりのようなエロエロしいクラスメイトが。
「わぁ、麦茶だ! ペットボトルじゃないんだ。うれし~」
そんな全身からにじみ出すエロさと裏腹に、椎名ちえりは、まるで子供のように無邪気なはしゃぎ声をあげた。クーラーをガンガンに効かせた部屋の中央には、こたつ兼用のダイニングテーブル。その上には二人分のグラスと、麦茶ポットが鎮座している。
「こういうのって、おうちの飲みものって感じがしてほっとするねぇ」
「ああ、言われてみればそうかもね」
「そうだよー。ゴザとー、茹でたトウモロコシとー、風鈴とー、それに花柄の麦茶ポットとー、汗のかいたグラス、みたいな?」
「昭和だなー」
べつにキャラを作っているふうでもなく、素朴な感慨を口にする彼女。見た目通りの今風ギャルだと思っていたのに、今まで縁遠かったクラスメイトの思わぬ姿を目にして、なんだか微笑ましい気分になる。
「でも、よく俺んちわかったな。クラス名簿とかに書いてあったっけ?」
「りょーちんに聞いたの」
「りょーちん?」
「センセだよ。ちょっと、こーちんにお願いしたいことがあったから」
「ああ──」
久保田涼一郎先生──穏和な性格が顔つきにまでにじみ出たかのような、クラス担任の姿を思い浮かべて納得する。学年主任も務めるベテラン教師で、生徒たちの間では「クボセン」なんて呼ばれて慕われている。
だが、お願いしたいことってなんだろう? 実は俺のことが好きだったとか? いやむしろ、べつに好きってわけじゃないけど、このぽっちゃり悩ましいダイナマイトボディに抱かれてみたいとか? もう普通のイケメンとは遊び飽きたから一周まわって非モテ童貞を躍り食いしたくなったとか──!?
「実はね、いきなりで、めちゃくちゃヘンで、めんどくさいこと言うかもしれないけど、あのね……あのね、あたし、こーちんに勉強を教えてほしいんだ」
「へっ?」
「そんな顔しないでよぉ。あたしも、らしくないって思うけど」
どうにもばつが悪そうに、彼女は話し始めた。
今までずっと、今が楽しければそれでいいと思っていたこと。だけど最近になって、いつまでも楽しいだけじゃダメかも、なんて思い始めたこと。先々のことを考えたら、勉強しなくちゃいけないような気がする。だけど家庭教師は頼めないし、でも一人でどうにかなりそうもないし──そこで入学以来、学年最上位の成績を維持し続けている、浩太に目をつけたというわけだ。できる人に勉強を見てもらえば、少しはゴリヤクがあるかもしれない、と。
「やっぱ、らしくないって思うよね」
「んー、まあ、驚いたのはたしかだけど」
「だよねえ……ヘンなこと頼んじゃってごめんね。麦茶ありがと……」
ほうっ、と深いため息をつく彼女。シュンと肩を落とすと、傍らに置いていたバッグに手を伸ばし、そそくさと帰り支度を始める──。
「どんくらい? たまにでいいの? それとも週二とか週三とか、ちゃんと決めてがっつりやったほうがいいのかな」
「へほっ?」
「いいよ、どうせ暇だし。それに人に教えるのも、いい勉強になるしな」
「ホントに!? 授業料? 的な? そーゆーのも出せないけど……」
「クラスメイトに勉強教えるぐらいで、金なんてとらないよ。椎名さんが真剣なのわかったし、そういうのって、すごくいいと思うよ」
と、調子のいい言葉を口から吐き出す浩太。
口にしたきれいごとの、半分ぐらいはまぎれもなく本心だ。だけど同時に、胸の中ではよからぬ期待も渦巻いている。こんなにもエロい身体の女の子と合法的に密室で二人きりなんて、これほどまでに童貞男子の胸をときめかせるシチュエーションがほかにあるだろうか。別にマンガやエロゲみたいなラッキースケベなんて起きなくてもかまわない。女の子と! 密室で! 二人きりの! 個人授業! 授業料どころか、むしろこちらが料金を支払いたいぐらいだ。
「よかったー。あたしみたいのがそんなこと言ったら、笑われるかと思っちゃったよ」
「なわけないだろ。まじめにがんばりたいって人を、笑うやつなんていないよ」
正直言えば、意外だった。
格好は派手だし、言動はゆるめだし──なんと言っても、制服でも隠しきれないお見事すぎるドスケベボディは、お年頃の男子生徒たちの妄想をどうしようもなく刺激する。「遊びまくっている今どきのギャル」のイメージを体現したかのような彼女が、こんな頼みごとをしてくるだなんて。
「だってあたし自分でも、絶対らしくないって思ってたもん。こーちん、いい人だぁ」
一瞬前までの緊張が、一気にほどけて彼女の表情が弛んだ。目を細めて、上目遣いにこちらを見上げる様子がなんともかわいらしい。そんな彼女を見下ろしていると、少女らしい無垢そのものの笑顔と、少女らしからぬ濃密な色香を放つ胸もとが同時に目に入り、愛らしさとイヤらしさのダブルパンチで軽く気が遠退いてしまう。
「で、勉強って、目標はどれくらい?」
「えっと、それは……定期試験で、追試を受けなくて済むくらい……?」
言いかけて、彼女がこちらを見上げてくる──。
「……じゃあ、ちょっとココロザシが低すぎるよね。えっと、それじゃあ、学年順位で五十番アップぐらいで」
「オッケー。椎名さんって、今、順位どれくらいだっけ?」
「──…………」
彼女の目が、ちらりと泳いだ。
きっと打ち明けるのも恥ずかしいぐらいの成績なんだろう。文?クラス一学年九百六十人の、おそらく最底辺グループ。
それなら、ちょっとしたコツを覚えるだけで、てきめんに成績は伸びるはずだ。あのへんの順位は平均三十点ぐらいでダンゴになっているから、選択問題を三つ四つ余分に正解するだけで、同レベルの連中を一気にごぼう抜きできる。暗記科目に絞って徹底的に試験対策をして、ヤマを張った範囲を集中的に反復させれば、五十位アップ、百位アップぐらいは難しくないだろう。
「よし、それじゃあ次の期末で……」
言いかけて、ふと口ごもる。
このいじらしいクラスメイトの力になってあげたい。だが同時に、一抹の下心も胸中を疼かせている。勉強を口実にしたら、彼女とお近づきになれないかなぁ、なんて……。
「いや、来学期だな。冬の期末考査で、学年三十位目標ってことでどうかな?」
「三十位っ!?」
「やっぱりキツいかな。冬まで勉強漬けっていうのは」
「ううん、今まで遊びすぎてたから、厳しいのはぜんぜんオッケーなんだけど……こーちんはいいの? 自分の勉強もあるでしょ?」
「やるからには、ちゃんとやるよ。目先のテストで点を取るだけじゃ意味ないだろ? 冬までに勉強の仕方まで身につけて、一人でもがんばれるようになってもらうから」
「うぅっ……!?」
彼女が見るからに動揺する。下心のせいで、ちょっとふっかけすぎただろうか──?
「で、でも、そうだよね……うん、三十位! あ、あのね……でも……」
「うん?」
「あのね……あたし、ほんと頭悪いよ? たぶん、こーちんが引いちゃうくらい」
「引いたりしないよ。自分から努力したいって人を、バカにするわけないだろ?」
「だってあたし、ほんとにバカなんだもん。もしかして……場合によっては、延長とかお願いしちゃっていいかな……?」
おずおずと、こちらを見つめてくる彼女。
なるほど「バカ」なんだろう、まるっきり打算も裏表も感じさせない、素直そのものの表情だった。きっと彼女は中途半端な優等生のように、小手先の試験テクニックで効率よく点数を取りたいわけじゃない。バカ正直にも、真正面からの努力で今までの自分を変えたいと願っているのだ。
「えっと、なんかゴメン」
「……なんでこーちんが謝るの?」
「なんでもないよ。よし、二学期末までがっちりやるぞ。いわゆる、魚を与えるんじゃなくて、魚の釣り方を教えろってやつだな」
そんな彼女に下心まじりで応じていた自分が、なんだか恥ずかしくなる。きっと彼女は思っていた以上に本気だし、根はマジメな性分なのだろう──。
「えっ、あの、あたし……釣りじゃなくて、勉強教えてほしいんだけど?」
だが本気だしマジメだけど、困ったことに、思っていた以上にバカなのかもしれない。ひとまずの区切りは二学期の期末考査。どうやら、なかなか前途多難な五ヶ月弱になりそうだった。
「わぁっ、おいしそう。こーちんって、お料理もできたんだ!?」
「そりゃまあ、一人暮らしだしな」
そんな彼女に、ひとまず魚と白飯を与えてみる。
アジの一夜干しをグリルで炙って、付け合わせはひじきの炒め煮に、ジッパー付きビニール袋で作ったキャベツの浅漬け。そろそろ陽も落ちて小腹も空いてきたけれど、クーラーの効いた室内から出たくない一心で二人分の夕食をこしらえたのだ。
「こういうのって嬉しいね。おうちごはんって感じがするね」
「んー……そうかな?」
言われてみれば、そうかもしれない。今までは「遊びすぎてた」ってぐらいだし、やはり外で食べることが多かったのだろうか。言われてみれば外食で焼き魚なんて、たしかにあんまり見ないような気がする。きっと居酒屋とか、小料理屋とか、オトナが行くような店なら、また別なんだろうけど──。
「どうかした?」
「いや、なんでもないけど……」
「ホントに? なんかこーちん、エロい目してるよ?」
心の中を読まれてしまったような気がして、トクンと鼓動が跳ねた。
一瞬、パパ的な男性といっしょに、いかにも大人っぽいお店で食事を楽しんでいる彼女の姿を思い浮かべてしまったのだ。ばつが悪くて視線を落とすと、今度はキャミソールの胸もとから今にもこぼれおちそうになっている、立派すぎる乳房が目に入ってくる。
「本当になんでもないから。椎名さん、がんばったなって思って」
その魅惑的な谷間に貼り付いてしまいそうな目をむりやり引き剥がし、テーブルのはしに重ねた解答用紙の束に視線をやる。
「がんばりすぎだよー。学校以外で、こんなに勉強したの初めてかも」
彼女の成績アップを図る前に、ひとまず現在の実力を把握しなくてはならない。そこで手元の問題集から、簡単なミニテストを解いてもらったのだ。主要どころの五教科×三十分で、間に休憩も挟んで三時間半。一通り終わったころには、すっかり気力を使い果たしてげんにゃりしていた彼女だったが、できたてのご飯を前にして、だいぶ元気を取り戻したようだった。
「ごめんね。なんだか、ご飯までごちそうになっちゃって」
「俺はぜんぜんかまわないけど、椎名さんは、親に連絡いれなくて大丈夫? けっこう遅くなっちゃったけど」
そう口にした途端、じっとこちらを見返してくる。
「それ、禁止」
「へっ?」
「だって、いちいちシイナサンって呼ばれるの、なんか堅苦しいんだもん」
「そんなこと言われても……」
「これから冬までいっしょに勉強するんだから、もっと仲良くならなきゃでしょ? じゃないとあたしも、こーちんのこと、室戸センセって呼んじゃうよ?」
無理無理無理、だって女の子だぞ──と心の中で困惑する。椎名さんがダメなら……ちえり? ちえりさん? ちえりちゃん? いやいやいや、女子相手にいきなり名前呼びなんて、童貞男子にはあまりにもハードルが高すぎる。
「だからね、ちーちゃんって呼んで」
「ちー……えり、さん……?」
「りぴーとあふたーみー、ちーちゃん?」
「ち、ちーちゃん……」
「はい、よくできました。これからよろしくね、こーちん」
浩太の目の前で、彼女が嬉しそうに目を細める。
見た目はギャル丸出しなのに、子供みたいに笑うんだな……と屈託のなさに気を呑まれてしまう。彼女みたいな派手めな女子は、自分みたいにパッとしない男なんて、小馬鹿にしているに違いないと思っていた。だけどこんなに素直だし、意外とマジメなところもあるし。これじゃ、見た目で相手を判断していたのは自分のほうじゃないか。
「ん。こちらこそよろしく」
ぎこちなく答えると、これまた彼女が素直そのものの微笑みを返してくる。
その笑みを見ていると、ますます自分自身の器の小ささを感じてしまう。ばつの悪い気分など覚えつつ、自分のぶんの茶碗をかき込みながらチラリと目をやる──。
「──……?」
すると彼女も箸を止め、にっこりこちらを見返してくる。
その素直そのものの視線に、どうにも気恥ずかしさを覚えてしまう。なんだよイイ子じゃないか、誰だよ、椎名さんの……ちーちゃんのことを、学園最エロスのズリネタクイーンだの、童貞チンポ千人斬りだの、好き勝手言ってた奴は──。
「なんか、やっぱりエロいこと考えてる?」
「ほ、本当になんでもないからっ」
だがイイ子だけど、やっぱりエロいのだ。
裏表のなさそうなキョトン顔が、全身から発散されるセックスの気配を際立たせて、ますます下腹のあたりがむずむずしてくる。それがどうにも気恥ずかしくて、浩太は再び、食事をかき込み始めた。
お年頃の娘さんのわりに、ちーちゃんはよく食べる女の子だった。
男子平均プラス二十キロの恵体を誇る浩太も、大食らいでは引けを取らない。久々に誰かと食べる晩ご飯はどうにも気分が弾んで、二人で炊飯器を空っぽにしてしまった。
あれだけ嬉しそうな顔を見せられると、料理した人間としてもなかなかに気分がいい。だが、よくあの食べっぷりで、完璧ボディを維持できるものだ。ひょっとして彼女は、余剰分のカロリーが、ぜんぶおっぱいに蓄積される便利体質なのだろうか……?
そんな楽しい晩御飯も終わり、今はミニテストの採点タイム。目の前で解答用紙をチェックされるのに耐えかねたらしく、ちーちゃんは自分から晩ご飯の後始末を買って出て、台所で洗い物をしている。
赤ペン片手に解答用紙に目を通すこと十分余り。一通り採点を終えて顔を上げると、流し台の前に立っている、彼女の後ろ姿が目に入った。
新婚さんって、こんな感じかな──なんて、つい余計な妄想をしてしまう。
今までおっぱいばかり見とれていたけれど、バックスタイルも負けず劣らずのエロさだった。太ももはむっちりと肉付きがいいし、小声の鼻歌にあわせてボリュームたっぷりのお尻が揺れているのもたまらない。こんがり小麦色に焼き上げられた肉々しい女体はかぶりついたらいかにもいい味がしそうで、思わずコクリと唾を呑み込んでしまう。
「それで、テストどうだったかなぁ……?」
キュキュッ、と蛇口を閉める音。
ちーちゃんが振り返った。だけど、目をそらすことができない。濡れた手をタオルで拭い、彼女がリビングに歩いてくる、その歩調に合わせて揺れるおっぱいに思わず視線を吸い寄せられてしまう──。
「……イヤ、見テマセンヨ?」
「見てたし! すっごい見てたし!」
「し、しかたないだろ! だって椎名さんが……」
「ちーちゃん」
「ちーちゃんが、そんなエロいカラダしてるからだよ! そりゃ見るよ!」
「こーちんって、はっきりとエロいよねえ」
そう言うなり、彼女はテーブルの対面に座り、ずいっ、と身を乗り出してきた。その動きに合わせて、ずずずいっ、とおっぱいがテーブルの天板を擦る。
「ま、ムッツリよりハッキリのほうがいいけどね。それで、テストはどうだった?」
ちーちゃんが、上目遣いでおずおずと尋ねてくる。浩太は解答用紙の束をまとめ、とん、とん、とん、とテーブルの上で揃えて──。
「とりあえず目標は冬の期末な。最初は勉強の習慣をつけることから始めよう」
「うん。それで、あの、点数は?」
「まずは習慣化だよ。勉強するぞーって特別に気張らなくても、ご飯を食べたり歯を磨いたりするみたいに、毎日、自然と勉強する習慣を身につけるのが最初のステップだな」
「えっと、こーちん、テストのほうは……」
「並行して小中学校の問題集もやってみよう。特に数学なんかは、わからないまま進めると、ますます苦手になっちゃうからね。当面は基礎の基礎からがっちり固めてみようか」
「悪かったのっ!? あたし、点数も教えられないくらいバカだったのっ!?」
「んー……」
彼女のたじろぎ顔を前に、ぱらぱらと解答用紙を見返してみる。
「国語はそこまで悪くないんだよね。古文はだめだけど、現代文でちゃんと点数取れてる。でも数学とか、そもそも公式を覚えてないと手も足も出ないタイプの問題は全滅。これは頭の出来がどうこうっていうより、単に勉強してない人の点数って気がするなあ」
「たしかに、今までぜんぜん勉強したことなかったけど……」
「たとえばさ、これ、どれぐらい暗記してる?」
「ほえっ?」
彼女に開いて見せたのは、古文の教科書の巻末についている助動詞の活用表。それをじっと見つめたあとで、不思議そうにこちらを見返してくる。
「これ、暗記するものだったの?」
「そうだよ。そのために、教科書に載ってるんだから」
「うそっ!? あたし、なんだかよくわかんない、ごちゃごちゃしたのが書いてあるなーって思ってた……」
つまりそれが、「勉強が苦手」ということなのだ。
一人でがんばろうとしても、そもそも、なにをどうがんばればいいのかわからない。だから机に向かって努力しようとしても、ただ漫然と教科書の文字列を追うだけになってしまうのだ。きっと、今の彼女はそんな状態なのだろう。
「ぜんぜん勉強してないのに現代文はそこそこ取れているんだから、地頭は悪くないってことだと思うんだ。読解力は全部の教科の基礎だから、普通に努力すれば、普通の成績は取れるようになると思うよ。そこから先は椎名さんの──」
言いかけて言葉を止める。
童貞気質が染みついているせいで、女子との距離感はいまいちわからない。「ちーちゃんの」と言い直そうとしたところで、彼女が真顔でこちらを見つめてるのに気がついた。
「あたしが想像以上にバカで引いちゃってない……?」
「そんなことないって」
「でもでも、たぶん、すっごくタイヘンだよ? あたしの相手で、お休みも全部潰れちゃうかもだよっ!?」
ずずずずずいっ、と身を乗り出してくる彼女。
テーブルに両肘をつき、吐息もかからんばかりに顔をつきあわせて……。目の前三十センチから見つめられるのが照れくさくて視線を落とすと、今度は前のめりになった身体から重力に引かれたおっぱいが垂れ下がり、テーブルの天板に乗っかっているのが見えた。キャミソールの胸もとからは、小麦色の谷間がだいぶ奥のほうまで覗けてしまっている。
「本当にそれぐらいがんばるなら、学園三十位くらい軽いと思うよ?」
「ん……だよね、信じる。三十位なんて絶対ムリって思ったけど、こーちんが言うなら取れる気がする。だって……」
そう言って、ちらりとこちらを見つめる彼女。
「こーちんって、すごく正直者だし……」
たしかに今、ものすごく欲望に正直に、小麦色の谷間を凝視してしまっていた。
だけど、今さら取り繕うのも逆に気恥ずかしい。おっぱいから顔を上げればプルプルの唇に目を奪われるし、横にそらせば剥き出しの肩が目に入ってくるし──こんなふうでは、居直りスケベを決め込む以外にどうしようもないではないか。
「ま、ちーちゃんみたいにエロい女の子と二人きりで勉強するってのは、男の夢みたいなもんだしな。放課後でも土日祝日でも、いくらでもつきあうからまかせとけって!」
「本当に正直さんだねぇ」
だいぶ失礼なことを言った気もするけど、気分を害したふうはない。それどころか彼女はテーブルの対面から、膝歩きで浩太の隣へとすり寄ってきた。
「でもさあ、いっこウソついてるでしょ?」
さわわっ……彼女の手が、浩太の肩を撫でた。
「い、いや、俺、ウソなんて……」
「オトコノコの夢は、勉強じゃなくて、そのあとのお楽しみなんじゃないの?」
そして反対の手で浩太の内ももに触れ、さすさす、さすさす……。むず痒くも心地よいその感触に下腹がヒクつき、キュウッ、と肛門のあたりに力が篭もる。
学園最エロス女子、椎名ちえりの童貞チンポ千人斬り伝説──!
彼女の様々な噂話が頭を駆け巡り、心臓が暴れる。
それを悟られまいと、深く息を吸って平然顔を作る。さわさわ、さすさす、さわさわ、さすさす……淫靡に、繊細に、まるで大きな舌でねぶりまわすかのように手のひらを這わせる彼女。そんな愛撫がたっぷり一分ほども続き──。
「ぜんぜん慌てたりしないね。意外とけーけんほーふ?」
「まさか。生まれたときからずっと、純度百パーセントの童貞だぞ」
そう答えている間にも浩太の下半身では、大きくなったペニスが脈打ち、窮屈そうにズボンを押し上げている。
「そっかぁ……でもゴメンね。こーちんの童貞引き受けるのはムリっぽい」
「えええええぇっ、この流れで、それはなくないっ!?」
「だってあたし、カレシいるから。こーちんとパコったら浮気になっちゃうし」
「そんな……そんな、マジかよ……」
自分でも信じられないくらい、情けない声が喉からあふれた。
きっと表情も、ひどく情けないしょんぼり顔になってしまっているに違いない。非モテ目デブ科に属する浩太としては、在学中、女っけなしですごすことぐらい覚悟しているつもりだった。だけど、こんなにもさわさわさすさすされて、思い切り期待を膨らませてからおあずけだなんて、あまりにも辛すぎる──。
「うわぁ……こーちんのカラダ、やわらかくて気持ちいいっ」
そんな男心なんて気付いたふうもなく、彼女がますます身体をすり寄せてくる。
浩太のすぐ隣りに寄り添って横抱きにしながら、今度は手のひらで腹のあたりをたぷたぷし始める。
からかっているのだろうか? どうせヤらせるつもりはないくせに、こんなにも柔らかな手で、こんなにもやらしい手付きで、さわさわ、さすさす、たぷたぷしてくるなんてあまりにもヒドすぎる。だけど、からかわれているのだとわかっていても、彼女の手付きはあまりにも気持ちよすぎて、止めることができないのだ……。
「うわ……お腹は柔らかいのに、こっちはカチカチだぁ」
その手が下腹のほうに触れ、ピクンと背中が震えた。
「いろいろお礼、しないといけないよね?」
「えっ、でも……浮気……」
「あたしねぇ、バカだけど、チンポしゃぶるのだけは、すっごい上手なんだぁ」
柔らかな身体が、むにゅっとくっついてくる。
「勉強を見てもらうかわりに、あたしはこーちんのチンポの面倒見てあげる。はい、脱いで? 上も、下も。お手伝いいる?」
その返事も待たずに、彼女の手がシャツの襟もとに伸びてくる。
シャツのボタンを外し、ズボンのベルトを弛め、ボクサーパンツを足から引き抜き……わけもわからず言いなりになっているうちに丸裸にされてしまう。促されるまま椅子にかけると、彼女はその足下に座り込んだ。
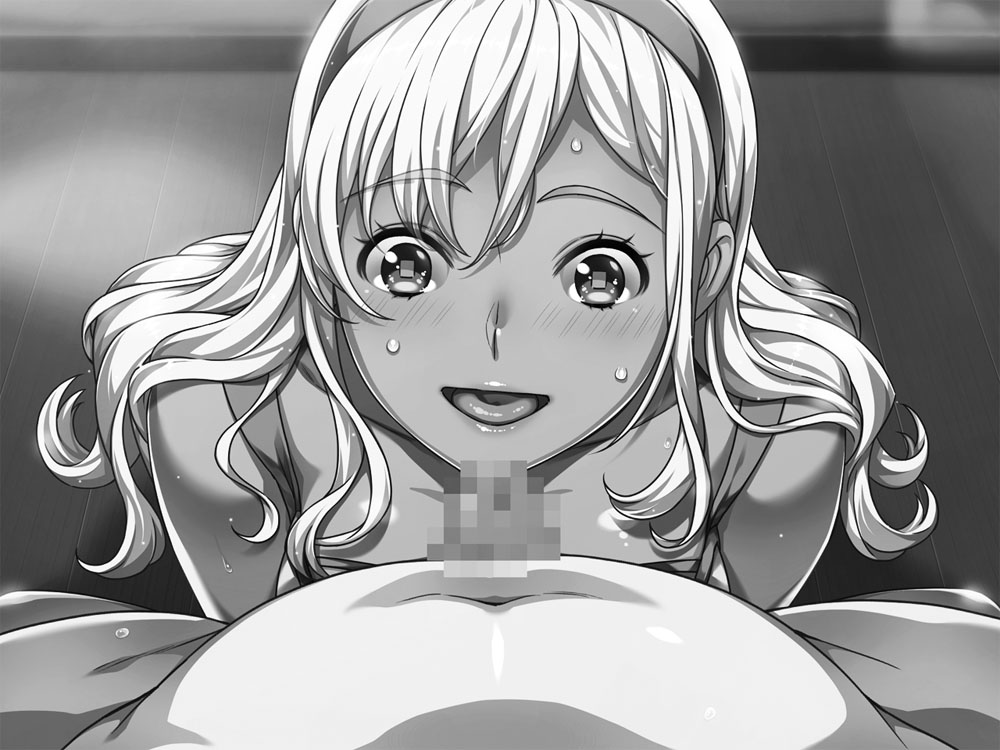
「ホンバンはできないけど、お口だけなら浮気にならないもんね。あはぁ……本当に大きいっ?」
弾んだ声と同時に、熱く湿った吐息がぬらりとペニスを舐める。
彼女が嬉しそうに舌なめずりをすると、ぷるぷるつやつやの唇がうっすらと湿り、なお色めいて艶光った。
「こーちんのチンポ、気になってたんだぁ。すっごい大きいって聞いてたから」
「うぉあっ!?」
彼女の指が、ペニスの根元から亀頭までをつるりと撫で上げた。
「水泳のあと、バカモリくんが大騒ぎしてたでしょ? こーちんは全学園制覇のチンポチャンピオンだーって。あはぁ……ホントに大きい?」
その言葉で、人のプライバシーを教室中に言いふらしやがった悪友の顔が頭に浮かんだ。
だがそれも一瞬、竿裏を撫でられる刺激が、浩太の頭から余計ごとを追い払ってしまう。すっ、すっ、すすすすっ、と指の腹がペニスを撫で上げるたび、快感が背骨を駆けあがり、おっ、おっ、と低い声が漏れ出てしまう。
「ほんとは今日、ずーっとコーフンしてたでしょ?」
彼女の顔がペニスに近付いてくる。
唇の体温を亀頭で感じ取れるくらい、ほんの間近まで。敏感な先端部を思わず温かな吐息にくすぐられて、思わずブルッと背中が震えた。
「だって、そういうニオイしてるもん。パンツのなかでずーっとボッキしっぱなしだった、蒸れ蒸れチンポのニオイ。んふっ……お口の中に、よだれ溜まってきちゃった」
言いながら、ぢゅるりと唾液をすすり上げる彼女。
「あたし、男の人のニオイ大好きなんだぁ。ごめんね、下品で」
「いや、俺としては、そういうのも大歓迎っていうか」
「引かない?」
「つか、むしろ興奮する……」
「ホントだ、こっちもよだれ垂らしちゃってる。こーちんの正直者っ?」
彼女の指が、先っぽのあたりをつるりと撫でた。
鈴口からはしたなく先走っていたカウパーの液玉が潰れ、ぬるぬるした汁が亀頭粘膜に染み込む。その体液臭を楽しむかのように、すんすんと鼻を鳴らす彼女。嬉しそうに目を細めながら、舌なめずりを二度、三度。チュクッ、とキスをひとつ。続いて愛しげに目を細め、上目遣いにこちらを見上げる。
「じゃあ、さっそく始めようか」
大好物の獲物を前にした、肉食獣のように優しい笑顔。直後、彼女の舌がペニスをぬらりと舐め上げてきた。
「う、あっ……!?」
思わず、カクンと膝が躍った。
ペニスが暴れ、彼女の鼻の頭を叩いた。だがそれにもかまわず、ますます激しく舌を絡ませてくる。たっぷりの唾液にまみれた舌が伸び、最初はペニスの根元からゆっくりと這い上がるように。ぬらぬらと汁あとを残しながら上ってくる舌先が、やがて竿と亀頭の境目に達して、裏スジのあたりをクリュクリュと舐めまわす。
「どおぉ? 初めてのベロフェラの感想は?」
「そ、それはっ……うぅっ……」
「んふっ……聞かなくてもわかるくらい、すっごい気持ちよさそうな声」
ぬちっ、ぬちゅっ、ぬちゅるるっ……その言葉と同時に、彼女の舌が激しく踊り始める。
指のように器用で、だのに指とはまったく違うやわらかさ、ぬめらかさ。肉厚の舌が、さながら軟体動物のようにペニスに絡みつくたび、激しい快感を覚える。ペニスが震え、肛門が締まり、内ももがヒクつき、膝が、足首が、さらにはつま先まで──その刺激が下半身全体に伝播してゆく。
「こーちん、今、すっごい顔してるよ?」
「今っ……か、顔、作ってる余裕、ないからっ」
「そういうの、格好つけないでちゃんと言えるんだ。オトコマエだね」
ちゅるるっ……彼女の舌が亀頭を這い上り、鈴口のほうへ。その敏感な粘膜穴を舌先でこそがれて、思わず膝が跳ね、足指がわきわきと蠢いた。
「んふっ……濃ゆいカウパーあふれて、口の中、火照ってきちゃう……」
うっとりと言いながら、鈴口へのディープキスを繰り返す彼女。
吸うように。ついばむように。こそぐように。くすぐるように。その一方で、彼女の指が会陰を撫で、内もものすじをさすり、陰嚢を甘揉みしてくる。ただ竿を握って上下にしごくだけの男子の日課とはまったく違う、繊細で執拗な愛戯。自分では触らないような隠れた性感帯を刺激する遠回りな指戯と、自分でも触らないような敏感すぎる尿道粘膜を狙った舌戯が、浩太の性感をたまらなく刺激する。下半身の筋肉に力が篭もって足首やふくらはぎに痛みを覚え──。
「もひかひて、ちょっと刺激強しゅぎ?」
「い、いやっ……そのまま、お願いします……」
「やっぱり、こーちんって正直だ。もっとサービスしたげるね?」
だが、それ以上の快感が浩太の全身を震わせる。
彼女の丹念な舌技で亀頭が溶け落ちて、一滴、一滴ずつ、どろどろした快感に変わりながら腹の底に溜まってゆくかのような感覚。下腹のあたりがずっしりと重く、深く腰を下ろしたまま息を荒らげる。だらしなく投げ出した手足が、彼女の舌愛撫に反応して、カクン、カクン、と跳ねる。
「はぁ……んん、男の人が気持ちよくひてると、あたひも感じちゃう。それに、おっきくて舐めがいあるし……こーちんって、すっごくフェラ向きの、いいチンポしてるよぉ」
もはや男の意地も体面も忘れて、されるがままの浩太。
軽く背中を反り、カクンと天井を仰ぎ、深く、深く息を吐く。
きっと彼女は、特別上手なんだろうな──。
されるがままに息を荒らげながら、そんなことを思う。
彼女以外の女子クラスメイトが、ペニスの扱いをこんなにも熟知しているとは思えない。毎日ペニスを握っている思春期男子も及ばないほど、男の歓ばせかたを熟知しきった巧みすぎる舌戯。きっと今まで、いろんな男のチンポをしゃぶりまくってきたんだろうな──ふとそんなことを思い、彼女の奔放すぎる性生活を想像して、ますます興奮が加速する。
「椎名さ……ちーちゃんって、すっごく、エロいな……」
「今さらなに言ってるの。いっつも、エロい目で見てたくせに」
彼女がついと唇を離した。
しまった、余計な一言だっただろうか──?
ずっと下半身を痺れさせていた激感が不意に消え、失望のため息が漏れる。それを聞いた彼女は、だが気分を害するどころか、どこか楽しげに目を細めた。
「なんでそんな情けない顔してるの。ほんと、スナオなんだから?」
そして、ペロリと舌なめずり。
深く息を吸うと、半開きの唇の奥で、そぼぼぼぼっ、と唾液の波立つ音が聞こえた。
頬をもにょもにょと動かし、唾液を口腔の隅々にまで行きわたらせる。そして舌を突き出し、大きく唇を開き、ゆっくりとペニスに顔を近づけ──。
「う、お、おぉっ……!?」
最初に感じたのは吐息の温度。
続いて、伸ばされた舌が亀頭の裏側に触れる。唾液にぬめる舌の上を亀頭が滑ってゆく。上唇が亀頭の先端あたりに触れ、続いてカリ首へ、さらに竿のほうまで……少しずつ、少しずつ、ペニスが彼女の口内に呑み込まれてゆく。
「あはぁ……やっふぁ大きい。アゴがはずれひゃいそう……」
ペニスを深く咥え込んだまま、彼女はもごもごと言った。
口腔粘膜のぬめらかさがたまらない。
肉厚の唇を丸く開いてペニスを咥え、上目遣いに見上げる表情がたまらない。
切なげな鼻息、上気した頬、唾液にぬめる口もと、汗ばんだ肌、濡れた額に貼り付く前髪──そのすべてがたまらない。ペニスを茹でる彼女の口内体温が、まるで頭のてっぺんにまで上ってきたかのようで、まぶたの裏あたりがカッと熱くなる。
「んん、ひゅごい……お口、いっぱいにくわえるとぉ……はふ、ん……チンポのにおい、いっぱい……」
彼女がもごもごと口にするたび、舌が、唇が、吐息がペニスを刺激してくる。
思わず射精感がこみ上げ──だが、下腹のあたりに力を込めて必死にこらえる。この極上の快感を、もっと、もっと味わっていたい。思わず腰が震え、彼女の口内をぐちゅぐちゅとかきまわした。
「あわてないれ。こえから、おくひまんこをたーっぷり味わわせてあげるから」
彼女はうっとりと両眼を細めた。
その声音も、どこか甘みを帯びているように感じる。浩太のペニスを愛撫しながら、まるで自分自身も感じているかのように。
「がまん、ひなくていいよ? 出したくなったら出しちゃって? 男の人のガマンしてる顔も好きらけどぉ……あたひ、飲むのも大好きらから」
ちゅこっ、ちゅこっ、ちゅこっ、ちゅこっ……ゆっくり、大きく首を振り始める。
ねっとりと貼り付く内頬。唾液でぬらつく口蓋。強く締めつけてくる唇。熱い口内では舌先がじゃれつくように踊り、亀頭笠のあたりをクリュクリュと刺激してくる。そのたびに腹の底が疼き、落ち着きなく腰をにじらせる。
「がまん、ひにゃいでって言ってるのに」
浩太の欲情に感染したかのように、彼女の顔がますます赤みを増した。口を塞がれて苦しいのだろうか、時折、首振りを止めて大きく息を吸う。その切なげな息遣いがたまらない。細めたまぶたの奥では、潤んだ瞳がうっとりとこちらを見上げてきていた。
「ヤバいよ、これ……気持ちよすぎ……」
それを聞いた彼女が、ますます嬉しそうに両目を細める。

今、感じてるんだ──!
そのことを確信して、ぞくぞくと背中が震えた。
フェラチオで感じるなんて、エロゲの中だけの話だと思っていた。
でも、彼女は違う。その肌の紅潮も、切なげな呼気も、潤んだ瞳もすべて本物だ。浩太の快感が彼女に感染し、彼女の淫猥さが浩太を急き立てる。うっとりと酔いしれながらペニスにしゃぶりつく、彼女の姿から目が離せなくなってしまう。
「まだらよ、もっと……もおぉっと、気持ひよくひてあげるからぁ」
その熱視線を浴びながら、いたずらっぽく微笑む彼女。
ずぞぞぞぞぞっ……唇の隙間から息を吸いあげる。口腔内で唾液が波立ち、竿肌に内頬が吸いついてきた。柔らかな口内粘膜にペニスを包まれ、んんっ、と思わず吐息まじりの声を漏らしてしまう。
「いちゅれも出ひちゃっていいからねぇ。れんぶ、飲んれあげるからぁ……」
その言葉と同時に、彼女は勢いよく首を振り始めた。
ぢゅぽっ! ぢゅぽっ! ぢゅぽっ!
汁音が鳴る。口腔全体でペニスを絞るように。ぺこんとくぼんだほっぺたの内側を竿肌に吸いつかせるように。ぴったり密着させた頬粘膜で、肉茎をぬらぬらと擦り上げるように。ずぞぞっ、ぢゅる、ぢゅぞぞぞぞぞぉっ……激しい首振りの傍ら、何度も強く吸引する。下品な音。淫らな表情。好色そうなまなざし。いかにも遊んでいそうなギャルっぽい彼女だけど、意外とマジメなところもあるんだな……今日一日、椎名ちえりという女の子とつきあってみて、そんなふうに思っていた。だけど「意外とマジメ」な顔のさらに下に隠されていたのは、クラスメイトたちの無責任な噂話をそのまま具現化したような、この上なく淫らな女の子だ。カフェオレ色の肌を上気させ、両頬にバキュームえくぼを浮かべ、あふれるよだれをすすり上げながら、大きく首振りを続ける彼女。温かくぬめる粘膜に強くペニスを擦り上げられて、思わず腰が動いてしまう。
「ちーちゃっ……すげ、エロいっ……俺っ……」
尻や腹筋がヒクつき、ペニスが大きく暴れた。
彼女の口からペニスが抜け、その拍子に、下唇でカリ首を擦られる。
下腹のあたりに蓄積していた快感のかたまりが出口を求めて渦巻いている。その欲望が睾丸を疼かせ、ペニスの根元を激しくノックする。激しくも丹念なフェラチオによって、たっぷり二十分ほどもかけて蓄積された重く熱い快感が、たった一回の射精になって出て行こうとしている。体内で暴れるその感覚に耐えかねて身を捩ると、ペニスもいっしょに激しく脈打った。その暴れるペニスを、高圧ホースと格闘する消防士さながらに御する彼女。高まりきったペニスを握ると、最後の仕上げとばかりに擦り上げる。ぬちゅっ、ぬちゅっ、ぬちゅっ、ぬちゅっ……唾液まみれの肉竿を右手でしごく、しごく。下腹が疼く。睾丸が疼く。竿の根元が疼く。くふっ、とくぐもった声が漏れる。
「お、俺っ……もっ、出るっ……」
続きは11月30日発売のオトナ文庫『バカだけどチンチンしゃぶるのだけはじょうずなちーちゃん』でお楽しみください!
(c)MINAMI EBINUMA/ORCSOFT
わけじゃないが、それでも口から漏れ出てしまう。
「あぢぃ……」
益体もない愚痴を漏らしながら、ずるずると重い足を引きずる。
学校指定のワイシャツの下には、男子平均プラス二十キロ分の分厚い脂肪のコート。梅雨明け間もない七月の街は、さながら一ヶ月後の盛夏を先取りしたかのような暑さで全身を茹であげてくる。大量の汗でシャツがべったりと貼り付き、一歩ごとにぬちゃぬちゃと湿った音が鳴る。
「あ、あぢいぃ……」
益体もない愚痴をもう一度。
本当なら、こんな日はクーラーの効いた室内でアイスクリームでもぱくついているべきだ。それこそがピザデブにとっての、正しい夏の過ごし方というものだ。だがそれでも、今日、明日分の食料品ぐらいは確保しておかないといけない。一人暮らしは気楽で快適だけど、こういうときは親のありがたさが──。
「……ま、無駄口叩いても、どうしようもないか」
三度目の愚痴を喉もとで押し止めて、茹だりきった身体をずるずると引きずる。片手にはずっしりと重いレジ袋。食料品の買い出しを終えたそれを自宅マンションまで運んだら、もう外出なんかしない。この土日は、室内に引きこもって自堕落で快適な生活を満喫するのだ──と。
「うっわ……」
そんなことを思いながら歩いていると、コンビニの駐車場にフェラチオが座り込んでいるのが目に入った。
いや、正確に言えば座り込んでいるのは、もはやフェラチオと呼ぶ以外ない、エロエロしいまでにエロい仕草でアイスキャンディーを舐めしゃぶっているエロ女だ。

脱色したロングヘアに、こんがり焼けた褐色肌。ボンキュッボンなワガママボディで、全身是セックスとでも言うべき、ただならないエロさを周囲に振りまいている。そんな肉感的にもほどがある身体を、ショート丈のヘソ出しキャミと膝上二十センチ超のミニスカートに押し込んで座り込んでいるものだから、ギャル服の下からはパンツが、上から立派すぎる谷間が覗いてしまっていた。
厚みのあるぽってりした唇でアイスキャンディーをちゅぱちゅぱと舐め回しているその姿は、さながら「アタシは棒状のモノをしゃぶるのがちょー得意です!」と主張するエロギャルのごとし。とろけたアイスが唇からこぼれ、顎から胸もとへと伝い、肌を濡らす汗に溶けながら乳房の丸みに沿って奥のほうへと流れ込んでゆく──その様子に目を奪われ、思わずコクリと唾を飲み込む。
「はふっ、はむ、んん、ん……」
そんな熱視線にも気付かず、べろんべろんとアイスキャンディーを舐め回す彼女。
物憂げそうな半開きの瞳。汗を吸って乳房に貼りつくキャミソール。だらしなく開いた両膝。小麦色の肌とコントラストを成すパンツの純白色。ああ、もうたまらない。今すぐ家に帰ってシコりたい……でも、もっとこの光景を見ていたい……でも見れば見るほど、今すぐシコりたくなってしまう! 夏の太陽に炙られた頭の中がドロドロにとろけてゆく一方、下半身に熱い血が集まり、ズボンの中がガチガチにこわばってゆく。
と、そのとき、彼女がご開帳状態だった両膝を閉じた。
ガッカリ感とともに顔を上げると、くりくりした瞳がこちらを見返しているのに気がついた。それから目を逸らしつつ、まださらけ出されている胸の谷間に視線を向ける──。
「いやいやいや、もっかい見直すとかありえないし!」
と、そんな不躾な視線を遮るように、目の前のセックスが両手を胸もとにやった。
いや正確に言えば、もはや全身是セックスというほかない、エロすぎる身体の女の子がだ。彼女は棒だけになったアイスキャンディーをゴミ箱に放り込むと、こちらに近づいてきた。ぴょこぴょこと軽快な足取り。しっとりと汗ばんだ太もも。たぷたぷと揺れるおっぱい。さらにもう二十センチばかり視線を上げたところで、エロすぎる身体の上に、よく見慣れた顔が載っているのに気がついた。
「もー。ちょっとは遠慮しなよね。まじまじガン見しちゃって」
「……せっかく見せてくれてるんだから、ありがたく見せてもらおうと思って」
「見せてるわけじゃないし! こーちんって、いい性格してるよねぇ」
大げさにあきれて見せるけど、表情も、声音にも怒気はない。
近づいてきたのは椎名ちえりだった。
豊満にもほどがある肢体で、いつも男子生徒たちの目を大いに愉しませたり、悩ませたりしているクラスメイト。なんでもブラジル方面の血が入っているらしく、亜麻色の髪やカフェオレ色の肌は生まれながらの天然物。ダイナマイトにもほどがあるプロポーションも、そちらの遺伝子のたまものだとか。オスの性本能を直接ぶん殴ってくるような刺激的すぎるボディと、いかにもゆるそうな人柄に惹かれてしまった男どもは数知れず。彼女と直接話したことはほとんどないけれど、経験豊富だの、エンコーでマンションを買っただの、我が校の男子生徒の大半は彼女の手ほどきで童貞喪失しているだの、どこまで本当なのかわからない噂話を幾つも耳にしている。いや、たぶん九割方ウソなんだろうけれど、そんな荒唐無稽な噂も「ひょっとして!?」と思わせてしまうかのような、彼女が暴力的なまでのエロさを備えたオンナであることは、まぎれもない事実なのだ。
「誰かと思った。私服の椎名さん見るの初めてだったから」
「服なんか見てなかったくせに」
せめてもの言い訳を、一言のもとに切り捨てる彼女。
だがやはり気分を害したふうはなく、むしろ楽しげにこちらを見返してくる。
素直で愛嬌のある人懐こい表情──だが、いかにも牝々しい身体つきでそんな顔をされると、あれこれ余計な妄想が膨らんでしまって、下腹のあたりがどうにも落ち着かない。
「会えてよかったよぉ。うちに行ったけど留守だったんだもん」
「うちって……俺んち?」
「うん。それで、ひょっとしたら会えるかもって思って、近くで待ってたんだ」
ずくん、と心臓が弾んだ。
クラスのエロい女子が俺に会うために家まで押しかけてきた? そんなの、童貞の夢物語だ。あるはずのない馬鹿話だ──。
「……なんで?」
「そりゃもちろん、用事があったからだよー。スマホのアドレス知らなかったから、直接来ちゃった」
その馬鹿みたいな夢物語が今、目の前でにこにこ顔を浮かべている。直射日光に脳天を炙られ、牝フェロモンに下腹を刺激され、胸中には甘酸っぱい期待が渦巻き──。
「続きは、こーちんちでね。じゃあ、しゅっぱつしんこー!」
わけもわからず呆けていると、彼女はぐいぐいと背中を押し始めた。
うわっ、手のひら柔らかいっ──!?
彼女の人懐こさと図々しさに面食らいながらも、その心地よい感触だけで、なにもかも許せる気分になってしまうのだった。
室戸浩太は、近所の学園に通う男子生徒だ。
今は親もとを離れ、通学用にワンルームのマンションを借りて一人暮らし。学生の一人暮らしなんてたちまち悪友どものたまり場になってしまいそうなものだが、そうなっていないのは、浩太自身が、あまり積極的に交友範囲を広げるタイプではないからだ。
かと言って、教室でいじめられているというわけでもない。
男子平均プラス二十キロのぽっちゃり体型だが、いわゆる「動けるデブ」というやつで、運動はむしろ得意なほうといっていい。その上、学業のほうは入学以来、常に学年トップクラスに居座り続けている。周囲からはそれなりに一目置かれているし、人づきあいが狭いのはべつに嫌われているわけではなく、一人でゲームやアニメを楽しむのが性に合っているインドア志向ゆえの選択の結果なのだ──と浩太自身は思っている。
だから一人暮らしのマンションも、今まで入ったことがあるのは浩太自身と、父親との二人きり。だが今日、その室内に思いがけない三人目が足を踏み入れた。エロい身体で、エロい格好で、エロい仕草が板についている、まるでエロのかたまりのようなエロエロしいクラスメイトが。
「わぁ、麦茶だ! ペットボトルじゃないんだ。うれし~」
そんな全身からにじみ出すエロさと裏腹に、椎名ちえりは、まるで子供のように無邪気なはしゃぎ声をあげた。クーラーをガンガンに効かせた部屋の中央には、こたつ兼用のダイニングテーブル。その上には二人分のグラスと、麦茶ポットが鎮座している。
「こういうのって、おうちの飲みものって感じがしてほっとするねぇ」
「ああ、言われてみればそうかもね」
「そうだよー。ゴザとー、茹でたトウモロコシとー、風鈴とー、それに花柄の麦茶ポットとー、汗のかいたグラス、みたいな?」
「昭和だなー」
べつにキャラを作っているふうでもなく、素朴な感慨を口にする彼女。見た目通りの今風ギャルだと思っていたのに、今まで縁遠かったクラスメイトの思わぬ姿を目にして、なんだか微笑ましい気分になる。
「でも、よく俺んちわかったな。クラス名簿とかに書いてあったっけ?」
「りょーちんに聞いたの」
「りょーちん?」
「センセだよ。ちょっと、こーちんにお願いしたいことがあったから」
「ああ──」
久保田涼一郎先生──穏和な性格が顔つきにまでにじみ出たかのような、クラス担任の姿を思い浮かべて納得する。学年主任も務めるベテラン教師で、生徒たちの間では「クボセン」なんて呼ばれて慕われている。
だが、お願いしたいことってなんだろう? 実は俺のことが好きだったとか? いやむしろ、べつに好きってわけじゃないけど、このぽっちゃり悩ましいダイナマイトボディに抱かれてみたいとか? もう普通のイケメンとは遊び飽きたから一周まわって非モテ童貞を躍り食いしたくなったとか──!?
「実はね、いきなりで、めちゃくちゃヘンで、めんどくさいこと言うかもしれないけど、あのね……あのね、あたし、こーちんに勉強を教えてほしいんだ」
「へっ?」
「そんな顔しないでよぉ。あたしも、らしくないって思うけど」
どうにもばつが悪そうに、彼女は話し始めた。
今までずっと、今が楽しければそれでいいと思っていたこと。だけど最近になって、いつまでも楽しいだけじゃダメかも、なんて思い始めたこと。先々のことを考えたら、勉強しなくちゃいけないような気がする。だけど家庭教師は頼めないし、でも一人でどうにかなりそうもないし──そこで入学以来、学年最上位の成績を維持し続けている、浩太に目をつけたというわけだ。できる人に勉強を見てもらえば、少しはゴリヤクがあるかもしれない、と。
「やっぱ、らしくないって思うよね」
「んー、まあ、驚いたのはたしかだけど」
「だよねえ……ヘンなこと頼んじゃってごめんね。麦茶ありがと……」
ほうっ、と深いため息をつく彼女。シュンと肩を落とすと、傍らに置いていたバッグに手を伸ばし、そそくさと帰り支度を始める──。
「どんくらい? たまにでいいの? それとも週二とか週三とか、ちゃんと決めてがっつりやったほうがいいのかな」
「へほっ?」
「いいよ、どうせ暇だし。それに人に教えるのも、いい勉強になるしな」
「ホントに!? 授業料? 的な? そーゆーのも出せないけど……」
「クラスメイトに勉強教えるぐらいで、金なんてとらないよ。椎名さんが真剣なのわかったし、そういうのって、すごくいいと思うよ」
と、調子のいい言葉を口から吐き出す浩太。
口にしたきれいごとの、半分ぐらいはまぎれもなく本心だ。だけど同時に、胸の中ではよからぬ期待も渦巻いている。こんなにもエロい身体の女の子と合法的に密室で二人きりなんて、これほどまでに童貞男子の胸をときめかせるシチュエーションがほかにあるだろうか。別にマンガやエロゲみたいなラッキースケベなんて起きなくてもかまわない。女の子と! 密室で! 二人きりの! 個人授業! 授業料どころか、むしろこちらが料金を支払いたいぐらいだ。
「よかったー。あたしみたいのがそんなこと言ったら、笑われるかと思っちゃったよ」
「なわけないだろ。まじめにがんばりたいって人を、笑うやつなんていないよ」
正直言えば、意外だった。
格好は派手だし、言動はゆるめだし──なんと言っても、制服でも隠しきれないお見事すぎるドスケベボディは、お年頃の男子生徒たちの妄想をどうしようもなく刺激する。「遊びまくっている今どきのギャル」のイメージを体現したかのような彼女が、こんな頼みごとをしてくるだなんて。
「だってあたし自分でも、絶対らしくないって思ってたもん。こーちん、いい人だぁ」
一瞬前までの緊張が、一気にほどけて彼女の表情が弛んだ。目を細めて、上目遣いにこちらを見上げる様子がなんともかわいらしい。そんな彼女を見下ろしていると、少女らしい無垢そのものの笑顔と、少女らしからぬ濃密な色香を放つ胸もとが同時に目に入り、愛らしさとイヤらしさのダブルパンチで軽く気が遠退いてしまう。
「で、勉強って、目標はどれくらい?」
「えっと、それは……定期試験で、追試を受けなくて済むくらい……?」
言いかけて、彼女がこちらを見上げてくる──。
「……じゃあ、ちょっとココロザシが低すぎるよね。えっと、それじゃあ、学年順位で五十番アップぐらいで」
「オッケー。椎名さんって、今、順位どれくらいだっけ?」
「──…………」
彼女の目が、ちらりと泳いだ。
きっと打ち明けるのも恥ずかしいぐらいの成績なんだろう。文?クラス一学年九百六十人の、おそらく最底辺グループ。
それなら、ちょっとしたコツを覚えるだけで、てきめんに成績は伸びるはずだ。あのへんの順位は平均三十点ぐらいでダンゴになっているから、選択問題を三つ四つ余分に正解するだけで、同レベルの連中を一気にごぼう抜きできる。暗記科目に絞って徹底的に試験対策をして、ヤマを張った範囲を集中的に反復させれば、五十位アップ、百位アップぐらいは難しくないだろう。
「よし、それじゃあ次の期末で……」
言いかけて、ふと口ごもる。
このいじらしいクラスメイトの力になってあげたい。だが同時に、一抹の下心も胸中を疼かせている。勉強を口実にしたら、彼女とお近づきになれないかなぁ、なんて……。
「いや、来学期だな。冬の期末考査で、学年三十位目標ってことでどうかな?」
「三十位っ!?」
「やっぱりキツいかな。冬まで勉強漬けっていうのは」
「ううん、今まで遊びすぎてたから、厳しいのはぜんぜんオッケーなんだけど……こーちんはいいの? 自分の勉強もあるでしょ?」
「やるからには、ちゃんとやるよ。目先のテストで点を取るだけじゃ意味ないだろ? 冬までに勉強の仕方まで身につけて、一人でもがんばれるようになってもらうから」
「うぅっ……!?」
彼女が見るからに動揺する。下心のせいで、ちょっとふっかけすぎただろうか──?
「で、でも、そうだよね……うん、三十位! あ、あのね……でも……」
「うん?」
「あのね……あたし、ほんと頭悪いよ? たぶん、こーちんが引いちゃうくらい」
「引いたりしないよ。自分から努力したいって人を、バカにするわけないだろ?」
「だってあたし、ほんとにバカなんだもん。もしかして……場合によっては、延長とかお願いしちゃっていいかな……?」
おずおずと、こちらを見つめてくる彼女。
なるほど「バカ」なんだろう、まるっきり打算も裏表も感じさせない、素直そのものの表情だった。きっと彼女は中途半端な優等生のように、小手先の試験テクニックで効率よく点数を取りたいわけじゃない。バカ正直にも、真正面からの努力で今までの自分を変えたいと願っているのだ。
「えっと、なんかゴメン」
「……なんでこーちんが謝るの?」
「なんでもないよ。よし、二学期末までがっちりやるぞ。いわゆる、魚を与えるんじゃなくて、魚の釣り方を教えろってやつだな」
そんな彼女に下心まじりで応じていた自分が、なんだか恥ずかしくなる。きっと彼女は思っていた以上に本気だし、根はマジメな性分なのだろう──。
「えっ、あの、あたし……釣りじゃなくて、勉強教えてほしいんだけど?」
だが本気だしマジメだけど、困ったことに、思っていた以上にバカなのかもしれない。ひとまずの区切りは二学期の期末考査。どうやら、なかなか前途多難な五ヶ月弱になりそうだった。
「わぁっ、おいしそう。こーちんって、お料理もできたんだ!?」
「そりゃまあ、一人暮らしだしな」
そんな彼女に、ひとまず魚と白飯を与えてみる。
アジの一夜干しをグリルで炙って、付け合わせはひじきの炒め煮に、ジッパー付きビニール袋で作ったキャベツの浅漬け。そろそろ陽も落ちて小腹も空いてきたけれど、クーラーの効いた室内から出たくない一心で二人分の夕食をこしらえたのだ。
「こういうのって嬉しいね。おうちごはんって感じがするね」
「んー……そうかな?」
言われてみれば、そうかもしれない。今までは「遊びすぎてた」ってぐらいだし、やはり外で食べることが多かったのだろうか。言われてみれば外食で焼き魚なんて、たしかにあんまり見ないような気がする。きっと居酒屋とか、小料理屋とか、オトナが行くような店なら、また別なんだろうけど──。
「どうかした?」
「いや、なんでもないけど……」
「ホントに? なんかこーちん、エロい目してるよ?」
心の中を読まれてしまったような気がして、トクンと鼓動が跳ねた。
一瞬、パパ的な男性といっしょに、いかにも大人っぽいお店で食事を楽しんでいる彼女の姿を思い浮かべてしまったのだ。ばつが悪くて視線を落とすと、今度はキャミソールの胸もとから今にもこぼれおちそうになっている、立派すぎる乳房が目に入ってくる。
「本当になんでもないから。椎名さん、がんばったなって思って」
その魅惑的な谷間に貼り付いてしまいそうな目をむりやり引き剥がし、テーブルのはしに重ねた解答用紙の束に視線をやる。
「がんばりすぎだよー。学校以外で、こんなに勉強したの初めてかも」
彼女の成績アップを図る前に、ひとまず現在の実力を把握しなくてはならない。そこで手元の問題集から、簡単なミニテストを解いてもらったのだ。主要どころの五教科×三十分で、間に休憩も挟んで三時間半。一通り終わったころには、すっかり気力を使い果たしてげんにゃりしていた彼女だったが、できたてのご飯を前にして、だいぶ元気を取り戻したようだった。
「ごめんね。なんだか、ご飯までごちそうになっちゃって」
「俺はぜんぜんかまわないけど、椎名さんは、親に連絡いれなくて大丈夫? けっこう遅くなっちゃったけど」
そう口にした途端、じっとこちらを見返してくる。
「それ、禁止」
「へっ?」
「だって、いちいちシイナサンって呼ばれるの、なんか堅苦しいんだもん」
「そんなこと言われても……」
「これから冬までいっしょに勉強するんだから、もっと仲良くならなきゃでしょ? じゃないとあたしも、こーちんのこと、室戸センセって呼んじゃうよ?」
無理無理無理、だって女の子だぞ──と心の中で困惑する。椎名さんがダメなら……ちえり? ちえりさん? ちえりちゃん? いやいやいや、女子相手にいきなり名前呼びなんて、童貞男子にはあまりにもハードルが高すぎる。
「だからね、ちーちゃんって呼んで」
「ちー……えり、さん……?」
「りぴーとあふたーみー、ちーちゃん?」
「ち、ちーちゃん……」
「はい、よくできました。これからよろしくね、こーちん」
浩太の目の前で、彼女が嬉しそうに目を細める。
見た目はギャル丸出しなのに、子供みたいに笑うんだな……と屈託のなさに気を呑まれてしまう。彼女みたいな派手めな女子は、自分みたいにパッとしない男なんて、小馬鹿にしているに違いないと思っていた。だけどこんなに素直だし、意外とマジメなところもあるし。これじゃ、見た目で相手を判断していたのは自分のほうじゃないか。
「ん。こちらこそよろしく」
ぎこちなく答えると、これまた彼女が素直そのものの微笑みを返してくる。
その笑みを見ていると、ますます自分自身の器の小ささを感じてしまう。ばつの悪い気分など覚えつつ、自分のぶんの茶碗をかき込みながらチラリと目をやる──。
「──……?」
すると彼女も箸を止め、にっこりこちらを見返してくる。
その素直そのものの視線に、どうにも気恥ずかしさを覚えてしまう。なんだよイイ子じゃないか、誰だよ、椎名さんの……ちーちゃんのことを、学園最エロスのズリネタクイーンだの、童貞チンポ千人斬りだの、好き勝手言ってた奴は──。
「なんか、やっぱりエロいこと考えてる?」
「ほ、本当になんでもないからっ」
だがイイ子だけど、やっぱりエロいのだ。
裏表のなさそうなキョトン顔が、全身から発散されるセックスの気配を際立たせて、ますます下腹のあたりがむずむずしてくる。それがどうにも気恥ずかしくて、浩太は再び、食事をかき込み始めた。
お年頃の娘さんのわりに、ちーちゃんはよく食べる女の子だった。
男子平均プラス二十キロの恵体を誇る浩太も、大食らいでは引けを取らない。久々に誰かと食べる晩ご飯はどうにも気分が弾んで、二人で炊飯器を空っぽにしてしまった。
あれだけ嬉しそうな顔を見せられると、料理した人間としてもなかなかに気分がいい。だが、よくあの食べっぷりで、完璧ボディを維持できるものだ。ひょっとして彼女は、余剰分のカロリーが、ぜんぶおっぱいに蓄積される便利体質なのだろうか……?
そんな楽しい晩御飯も終わり、今はミニテストの採点タイム。目の前で解答用紙をチェックされるのに耐えかねたらしく、ちーちゃんは自分から晩ご飯の後始末を買って出て、台所で洗い物をしている。
赤ペン片手に解答用紙に目を通すこと十分余り。一通り採点を終えて顔を上げると、流し台の前に立っている、彼女の後ろ姿が目に入った。
新婚さんって、こんな感じかな──なんて、つい余計な妄想をしてしまう。
今までおっぱいばかり見とれていたけれど、バックスタイルも負けず劣らずのエロさだった。太ももはむっちりと肉付きがいいし、小声の鼻歌にあわせてボリュームたっぷりのお尻が揺れているのもたまらない。こんがり小麦色に焼き上げられた肉々しい女体はかぶりついたらいかにもいい味がしそうで、思わずコクリと唾を呑み込んでしまう。
「それで、テストどうだったかなぁ……?」
キュキュッ、と蛇口を閉める音。
ちーちゃんが振り返った。だけど、目をそらすことができない。濡れた手をタオルで拭い、彼女がリビングに歩いてくる、その歩調に合わせて揺れるおっぱいに思わず視線を吸い寄せられてしまう──。
「……イヤ、見テマセンヨ?」
「見てたし! すっごい見てたし!」
「し、しかたないだろ! だって椎名さんが……」
「ちーちゃん」
「ちーちゃんが、そんなエロいカラダしてるからだよ! そりゃ見るよ!」
「こーちんって、はっきりとエロいよねえ」
そう言うなり、彼女はテーブルの対面に座り、ずいっ、と身を乗り出してきた。その動きに合わせて、ずずずいっ、とおっぱいがテーブルの天板を擦る。
「ま、ムッツリよりハッキリのほうがいいけどね。それで、テストはどうだった?」
ちーちゃんが、上目遣いでおずおずと尋ねてくる。浩太は解答用紙の束をまとめ、とん、とん、とん、とテーブルの上で揃えて──。
「とりあえず目標は冬の期末な。最初は勉強の習慣をつけることから始めよう」
「うん。それで、あの、点数は?」
「まずは習慣化だよ。勉強するぞーって特別に気張らなくても、ご飯を食べたり歯を磨いたりするみたいに、毎日、自然と勉強する習慣を身につけるのが最初のステップだな」
「えっと、こーちん、テストのほうは……」
「並行して小中学校の問題集もやってみよう。特に数学なんかは、わからないまま進めると、ますます苦手になっちゃうからね。当面は基礎の基礎からがっちり固めてみようか」
「悪かったのっ!? あたし、点数も教えられないくらいバカだったのっ!?」
「んー……」
彼女のたじろぎ顔を前に、ぱらぱらと解答用紙を見返してみる。
「国語はそこまで悪くないんだよね。古文はだめだけど、現代文でちゃんと点数取れてる。でも数学とか、そもそも公式を覚えてないと手も足も出ないタイプの問題は全滅。これは頭の出来がどうこうっていうより、単に勉強してない人の点数って気がするなあ」
「たしかに、今までぜんぜん勉強したことなかったけど……」
「たとえばさ、これ、どれぐらい暗記してる?」
「ほえっ?」
彼女に開いて見せたのは、古文の教科書の巻末についている助動詞の活用表。それをじっと見つめたあとで、不思議そうにこちらを見返してくる。
「これ、暗記するものだったの?」
「そうだよ。そのために、教科書に載ってるんだから」
「うそっ!? あたし、なんだかよくわかんない、ごちゃごちゃしたのが書いてあるなーって思ってた……」
つまりそれが、「勉強が苦手」ということなのだ。
一人でがんばろうとしても、そもそも、なにをどうがんばればいいのかわからない。だから机に向かって努力しようとしても、ただ漫然と教科書の文字列を追うだけになってしまうのだ。きっと、今の彼女はそんな状態なのだろう。
「ぜんぜん勉強してないのに現代文はそこそこ取れているんだから、地頭は悪くないってことだと思うんだ。読解力は全部の教科の基礎だから、普通に努力すれば、普通の成績は取れるようになると思うよ。そこから先は椎名さんの──」
言いかけて言葉を止める。
童貞気質が染みついているせいで、女子との距離感はいまいちわからない。「ちーちゃんの」と言い直そうとしたところで、彼女が真顔でこちらを見つめてるのに気がついた。
「あたしが想像以上にバカで引いちゃってない……?」
「そんなことないって」
「でもでも、たぶん、すっごくタイヘンだよ? あたしの相手で、お休みも全部潰れちゃうかもだよっ!?」
ずずずずずいっ、と身を乗り出してくる彼女。
テーブルに両肘をつき、吐息もかからんばかりに顔をつきあわせて……。目の前三十センチから見つめられるのが照れくさくて視線を落とすと、今度は前のめりになった身体から重力に引かれたおっぱいが垂れ下がり、テーブルの天板に乗っかっているのが見えた。キャミソールの胸もとからは、小麦色の谷間がだいぶ奥のほうまで覗けてしまっている。
「本当にそれぐらいがんばるなら、学園三十位くらい軽いと思うよ?」
「ん……だよね、信じる。三十位なんて絶対ムリって思ったけど、こーちんが言うなら取れる気がする。だって……」
そう言って、ちらりとこちらを見つめる彼女。
「こーちんって、すごく正直者だし……」
たしかに今、ものすごく欲望に正直に、小麦色の谷間を凝視してしまっていた。
だけど、今さら取り繕うのも逆に気恥ずかしい。おっぱいから顔を上げればプルプルの唇に目を奪われるし、横にそらせば剥き出しの肩が目に入ってくるし──こんなふうでは、居直りスケベを決め込む以外にどうしようもないではないか。
「ま、ちーちゃんみたいにエロい女の子と二人きりで勉強するってのは、男の夢みたいなもんだしな。放課後でも土日祝日でも、いくらでもつきあうからまかせとけって!」
「本当に正直さんだねぇ」
だいぶ失礼なことを言った気もするけど、気分を害したふうはない。それどころか彼女はテーブルの対面から、膝歩きで浩太の隣へとすり寄ってきた。
「でもさあ、いっこウソついてるでしょ?」
さわわっ……彼女の手が、浩太の肩を撫でた。
「い、いや、俺、ウソなんて……」
「オトコノコの夢は、勉強じゃなくて、そのあとのお楽しみなんじゃないの?」
そして反対の手で浩太の内ももに触れ、さすさす、さすさす……。むず痒くも心地よいその感触に下腹がヒクつき、キュウッ、と肛門のあたりに力が篭もる。
学園最エロス女子、椎名ちえりの童貞チンポ千人斬り伝説──!
彼女の様々な噂話が頭を駆け巡り、心臓が暴れる。
それを悟られまいと、深く息を吸って平然顔を作る。さわさわ、さすさす、さわさわ、さすさす……淫靡に、繊細に、まるで大きな舌でねぶりまわすかのように手のひらを這わせる彼女。そんな愛撫がたっぷり一分ほども続き──。
「ぜんぜん慌てたりしないね。意外とけーけんほーふ?」
「まさか。生まれたときからずっと、純度百パーセントの童貞だぞ」
そう答えている間にも浩太の下半身では、大きくなったペニスが脈打ち、窮屈そうにズボンを押し上げている。
「そっかぁ……でもゴメンね。こーちんの童貞引き受けるのはムリっぽい」
「えええええぇっ、この流れで、それはなくないっ!?」
「だってあたし、カレシいるから。こーちんとパコったら浮気になっちゃうし」
「そんな……そんな、マジかよ……」
自分でも信じられないくらい、情けない声が喉からあふれた。
きっと表情も、ひどく情けないしょんぼり顔になってしまっているに違いない。非モテ目デブ科に属する浩太としては、在学中、女っけなしですごすことぐらい覚悟しているつもりだった。だけど、こんなにもさわさわさすさすされて、思い切り期待を膨らませてからおあずけだなんて、あまりにも辛すぎる──。
「うわぁ……こーちんのカラダ、やわらかくて気持ちいいっ」
そんな男心なんて気付いたふうもなく、彼女がますます身体をすり寄せてくる。
浩太のすぐ隣りに寄り添って横抱きにしながら、今度は手のひらで腹のあたりをたぷたぷし始める。
からかっているのだろうか? どうせヤらせるつもりはないくせに、こんなにも柔らかな手で、こんなにもやらしい手付きで、さわさわ、さすさす、たぷたぷしてくるなんてあまりにもヒドすぎる。だけど、からかわれているのだとわかっていても、彼女の手付きはあまりにも気持ちよすぎて、止めることができないのだ……。
「うわ……お腹は柔らかいのに、こっちはカチカチだぁ」
その手が下腹のほうに触れ、ピクンと背中が震えた。
「いろいろお礼、しないといけないよね?」
「えっ、でも……浮気……」
「あたしねぇ、バカだけど、チンポしゃぶるのだけは、すっごい上手なんだぁ」
柔らかな身体が、むにゅっとくっついてくる。
「勉強を見てもらうかわりに、あたしはこーちんのチンポの面倒見てあげる。はい、脱いで? 上も、下も。お手伝いいる?」
その返事も待たずに、彼女の手がシャツの襟もとに伸びてくる。
シャツのボタンを外し、ズボンのベルトを弛め、ボクサーパンツを足から引き抜き……わけもわからず言いなりになっているうちに丸裸にされてしまう。促されるまま椅子にかけると、彼女はその足下に座り込んだ。
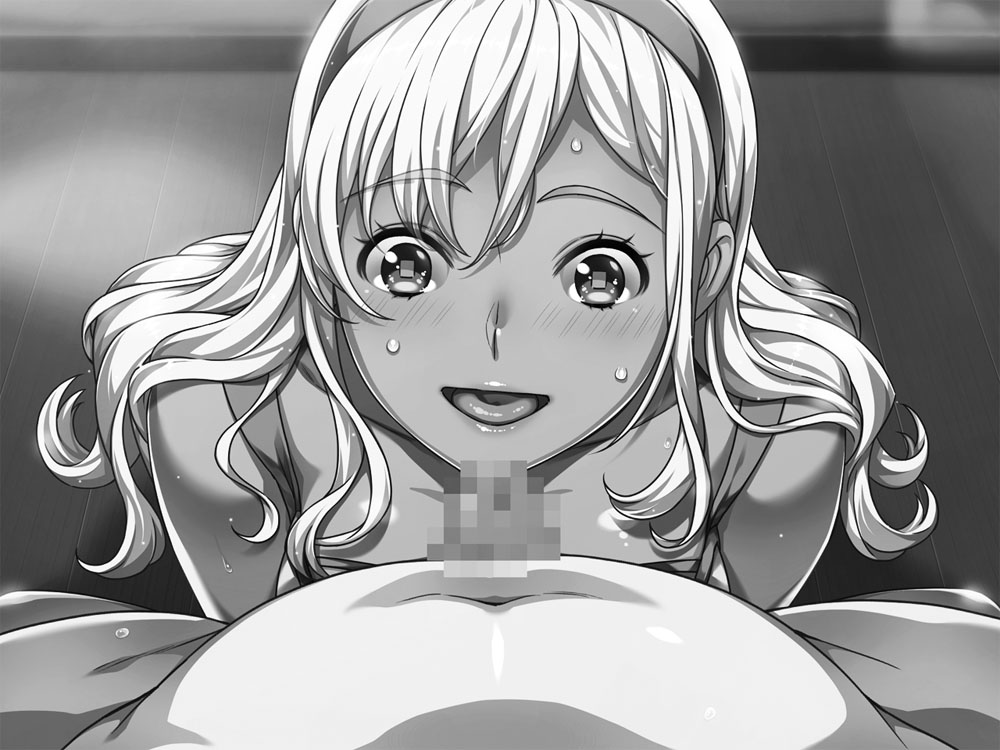
「ホンバンはできないけど、お口だけなら浮気にならないもんね。あはぁ……本当に大きいっ?」
弾んだ声と同時に、熱く湿った吐息がぬらりとペニスを舐める。
彼女が嬉しそうに舌なめずりをすると、ぷるぷるつやつやの唇がうっすらと湿り、なお色めいて艶光った。
「こーちんのチンポ、気になってたんだぁ。すっごい大きいって聞いてたから」
「うぉあっ!?」
彼女の指が、ペニスの根元から亀頭までをつるりと撫で上げた。
「水泳のあと、バカモリくんが大騒ぎしてたでしょ? こーちんは全学園制覇のチンポチャンピオンだーって。あはぁ……ホントに大きい?」
その言葉で、人のプライバシーを教室中に言いふらしやがった悪友の顔が頭に浮かんだ。
だがそれも一瞬、竿裏を撫でられる刺激が、浩太の頭から余計ごとを追い払ってしまう。すっ、すっ、すすすすっ、と指の腹がペニスを撫で上げるたび、快感が背骨を駆けあがり、おっ、おっ、と低い声が漏れ出てしまう。
「ほんとは今日、ずーっとコーフンしてたでしょ?」
彼女の顔がペニスに近付いてくる。
唇の体温を亀頭で感じ取れるくらい、ほんの間近まで。敏感な先端部を思わず温かな吐息にくすぐられて、思わずブルッと背中が震えた。
「だって、そういうニオイしてるもん。パンツのなかでずーっとボッキしっぱなしだった、蒸れ蒸れチンポのニオイ。んふっ……お口の中に、よだれ溜まってきちゃった」
言いながら、ぢゅるりと唾液をすすり上げる彼女。
「あたし、男の人のニオイ大好きなんだぁ。ごめんね、下品で」
「いや、俺としては、そういうのも大歓迎っていうか」
「引かない?」
「つか、むしろ興奮する……」
「ホントだ、こっちもよだれ垂らしちゃってる。こーちんの正直者っ?」
彼女の指が、先っぽのあたりをつるりと撫でた。
鈴口からはしたなく先走っていたカウパーの液玉が潰れ、ぬるぬるした汁が亀頭粘膜に染み込む。その体液臭を楽しむかのように、すんすんと鼻を鳴らす彼女。嬉しそうに目を細めながら、舌なめずりを二度、三度。チュクッ、とキスをひとつ。続いて愛しげに目を細め、上目遣いにこちらを見上げる。
「じゃあ、さっそく始めようか」
大好物の獲物を前にした、肉食獣のように優しい笑顔。直後、彼女の舌がペニスをぬらりと舐め上げてきた。
「う、あっ……!?」
思わず、カクンと膝が躍った。
ペニスが暴れ、彼女の鼻の頭を叩いた。だがそれにもかまわず、ますます激しく舌を絡ませてくる。たっぷりの唾液にまみれた舌が伸び、最初はペニスの根元からゆっくりと這い上がるように。ぬらぬらと汁あとを残しながら上ってくる舌先が、やがて竿と亀頭の境目に達して、裏スジのあたりをクリュクリュと舐めまわす。
「どおぉ? 初めてのベロフェラの感想は?」
「そ、それはっ……うぅっ……」
「んふっ……聞かなくてもわかるくらい、すっごい気持ちよさそうな声」
ぬちっ、ぬちゅっ、ぬちゅるるっ……その言葉と同時に、彼女の舌が激しく踊り始める。
指のように器用で、だのに指とはまったく違うやわらかさ、ぬめらかさ。肉厚の舌が、さながら軟体動物のようにペニスに絡みつくたび、激しい快感を覚える。ペニスが震え、肛門が締まり、内ももがヒクつき、膝が、足首が、さらにはつま先まで──その刺激が下半身全体に伝播してゆく。
「こーちん、今、すっごい顔してるよ?」
「今っ……か、顔、作ってる余裕、ないからっ」
「そういうの、格好つけないでちゃんと言えるんだ。オトコマエだね」
ちゅるるっ……彼女の舌が亀頭を這い上り、鈴口のほうへ。その敏感な粘膜穴を舌先でこそがれて、思わず膝が跳ね、足指がわきわきと蠢いた。
「んふっ……濃ゆいカウパーあふれて、口の中、火照ってきちゃう……」
うっとりと言いながら、鈴口へのディープキスを繰り返す彼女。
吸うように。ついばむように。こそぐように。くすぐるように。その一方で、彼女の指が会陰を撫で、内もものすじをさすり、陰嚢を甘揉みしてくる。ただ竿を握って上下にしごくだけの男子の日課とはまったく違う、繊細で執拗な愛戯。自分では触らないような隠れた性感帯を刺激する遠回りな指戯と、自分でも触らないような敏感すぎる尿道粘膜を狙った舌戯が、浩太の性感をたまらなく刺激する。下半身の筋肉に力が篭もって足首やふくらはぎに痛みを覚え──。
「もひかひて、ちょっと刺激強しゅぎ?」
「い、いやっ……そのまま、お願いします……」
「やっぱり、こーちんって正直だ。もっとサービスしたげるね?」
だが、それ以上の快感が浩太の全身を震わせる。
彼女の丹念な舌技で亀頭が溶け落ちて、一滴、一滴ずつ、どろどろした快感に変わりながら腹の底に溜まってゆくかのような感覚。下腹のあたりがずっしりと重く、深く腰を下ろしたまま息を荒らげる。だらしなく投げ出した手足が、彼女の舌愛撫に反応して、カクン、カクン、と跳ねる。
「はぁ……んん、男の人が気持ちよくひてると、あたひも感じちゃう。それに、おっきくて舐めがいあるし……こーちんって、すっごくフェラ向きの、いいチンポしてるよぉ」
もはや男の意地も体面も忘れて、されるがままの浩太。
軽く背中を反り、カクンと天井を仰ぎ、深く、深く息を吐く。
きっと彼女は、特別上手なんだろうな──。
されるがままに息を荒らげながら、そんなことを思う。
彼女以外の女子クラスメイトが、ペニスの扱いをこんなにも熟知しているとは思えない。毎日ペニスを握っている思春期男子も及ばないほど、男の歓ばせかたを熟知しきった巧みすぎる舌戯。きっと今まで、いろんな男のチンポをしゃぶりまくってきたんだろうな──ふとそんなことを思い、彼女の奔放すぎる性生活を想像して、ますます興奮が加速する。
「椎名さ……ちーちゃんって、すっごく、エロいな……」
「今さらなに言ってるの。いっつも、エロい目で見てたくせに」
彼女がついと唇を離した。
しまった、余計な一言だっただろうか──?
ずっと下半身を痺れさせていた激感が不意に消え、失望のため息が漏れる。それを聞いた彼女は、だが気分を害するどころか、どこか楽しげに目を細めた。
「なんでそんな情けない顔してるの。ほんと、スナオなんだから?」
そして、ペロリと舌なめずり。
深く息を吸うと、半開きの唇の奥で、そぼぼぼぼっ、と唾液の波立つ音が聞こえた。
頬をもにょもにょと動かし、唾液を口腔の隅々にまで行きわたらせる。そして舌を突き出し、大きく唇を開き、ゆっくりとペニスに顔を近づけ──。
「う、お、おぉっ……!?」
最初に感じたのは吐息の温度。
続いて、伸ばされた舌が亀頭の裏側に触れる。唾液にぬめる舌の上を亀頭が滑ってゆく。上唇が亀頭の先端あたりに触れ、続いてカリ首へ、さらに竿のほうまで……少しずつ、少しずつ、ペニスが彼女の口内に呑み込まれてゆく。
「あはぁ……やっふぁ大きい。アゴがはずれひゃいそう……」
ペニスを深く咥え込んだまま、彼女はもごもごと言った。
口腔粘膜のぬめらかさがたまらない。
肉厚の唇を丸く開いてペニスを咥え、上目遣いに見上げる表情がたまらない。
切なげな鼻息、上気した頬、唾液にぬめる口もと、汗ばんだ肌、濡れた額に貼り付く前髪──そのすべてがたまらない。ペニスを茹でる彼女の口内体温が、まるで頭のてっぺんにまで上ってきたかのようで、まぶたの裏あたりがカッと熱くなる。
「んん、ひゅごい……お口、いっぱいにくわえるとぉ……はふ、ん……チンポのにおい、いっぱい……」
彼女がもごもごと口にするたび、舌が、唇が、吐息がペニスを刺激してくる。
思わず射精感がこみ上げ──だが、下腹のあたりに力を込めて必死にこらえる。この極上の快感を、もっと、もっと味わっていたい。思わず腰が震え、彼女の口内をぐちゅぐちゅとかきまわした。
「あわてないれ。こえから、おくひまんこをたーっぷり味わわせてあげるから」
彼女はうっとりと両眼を細めた。
その声音も、どこか甘みを帯びているように感じる。浩太のペニスを愛撫しながら、まるで自分自身も感じているかのように。
「がまん、ひなくていいよ? 出したくなったら出しちゃって? 男の人のガマンしてる顔も好きらけどぉ……あたひ、飲むのも大好きらから」
ちゅこっ、ちゅこっ、ちゅこっ、ちゅこっ……ゆっくり、大きく首を振り始める。
ねっとりと貼り付く内頬。唾液でぬらつく口蓋。強く締めつけてくる唇。熱い口内では舌先がじゃれつくように踊り、亀頭笠のあたりをクリュクリュと刺激してくる。そのたびに腹の底が疼き、落ち着きなく腰をにじらせる。
「がまん、ひにゃいでって言ってるのに」
浩太の欲情に感染したかのように、彼女の顔がますます赤みを増した。口を塞がれて苦しいのだろうか、時折、首振りを止めて大きく息を吸う。その切なげな息遣いがたまらない。細めたまぶたの奥では、潤んだ瞳がうっとりとこちらを見上げてきていた。
「ヤバいよ、これ……気持ちよすぎ……」
それを聞いた彼女が、ますます嬉しそうに両目を細める。

今、感じてるんだ──!
そのことを確信して、ぞくぞくと背中が震えた。
フェラチオで感じるなんて、エロゲの中だけの話だと思っていた。
でも、彼女は違う。その肌の紅潮も、切なげな呼気も、潤んだ瞳もすべて本物だ。浩太の快感が彼女に感染し、彼女の淫猥さが浩太を急き立てる。うっとりと酔いしれながらペニスにしゃぶりつく、彼女の姿から目が離せなくなってしまう。
「まだらよ、もっと……もおぉっと、気持ひよくひてあげるからぁ」
その熱視線を浴びながら、いたずらっぽく微笑む彼女。
ずぞぞぞぞぞっ……唇の隙間から息を吸いあげる。口腔内で唾液が波立ち、竿肌に内頬が吸いついてきた。柔らかな口内粘膜にペニスを包まれ、んんっ、と思わず吐息まじりの声を漏らしてしまう。
「いちゅれも出ひちゃっていいからねぇ。れんぶ、飲んれあげるからぁ……」
その言葉と同時に、彼女は勢いよく首を振り始めた。
ぢゅぽっ! ぢゅぽっ! ぢゅぽっ!
汁音が鳴る。口腔全体でペニスを絞るように。ぺこんとくぼんだほっぺたの内側を竿肌に吸いつかせるように。ぴったり密着させた頬粘膜で、肉茎をぬらぬらと擦り上げるように。ずぞぞっ、ぢゅる、ぢゅぞぞぞぞぞぉっ……激しい首振りの傍ら、何度も強く吸引する。下品な音。淫らな表情。好色そうなまなざし。いかにも遊んでいそうなギャルっぽい彼女だけど、意外とマジメなところもあるんだな……今日一日、椎名ちえりという女の子とつきあってみて、そんなふうに思っていた。だけど「意外とマジメ」な顔のさらに下に隠されていたのは、クラスメイトたちの無責任な噂話をそのまま具現化したような、この上なく淫らな女の子だ。カフェオレ色の肌を上気させ、両頬にバキュームえくぼを浮かべ、あふれるよだれをすすり上げながら、大きく首振りを続ける彼女。温かくぬめる粘膜に強くペニスを擦り上げられて、思わず腰が動いてしまう。
「ちーちゃっ……すげ、エロいっ……俺っ……」
尻や腹筋がヒクつき、ペニスが大きく暴れた。
彼女の口からペニスが抜け、その拍子に、下唇でカリ首を擦られる。
下腹のあたりに蓄積していた快感のかたまりが出口を求めて渦巻いている。その欲望が睾丸を疼かせ、ペニスの根元を激しくノックする。激しくも丹念なフェラチオによって、たっぷり二十分ほどもかけて蓄積された重く熱い快感が、たった一回の射精になって出て行こうとしている。体内で暴れるその感覚に耐えかねて身を捩ると、ペニスもいっしょに激しく脈打った。その暴れるペニスを、高圧ホースと格闘する消防士さながらに御する彼女。高まりきったペニスを握ると、最後の仕上げとばかりに擦り上げる。ぬちゅっ、ぬちゅっ、ぬちゅっ、ぬちゅっ……唾液まみれの肉竿を右手でしごく、しごく。下腹が疼く。睾丸が疼く。竿の根元が疼く。くふっ、とくぐもった声が漏れる。
「お、俺っ……もっ、出るっ……」
続きは11月30日発売のオトナ文庫『バカだけどチンチンしゃぶるのだけはじょうずなちーちゃん』でお楽しみください!
(c)MINAMI EBINUMA/ORCSOFT




